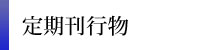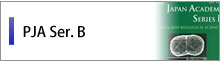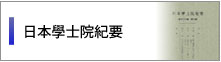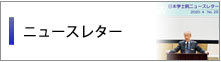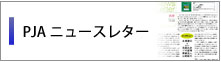日本学士院第13回学びのススメシリーズ講演会のお知らせ

パンフレットダウンロード
日本学士院学びのススメシリーズ講演会は、様々な分野で素晴らしい研究を重ねてきた日本学士院会員が、日本の将来の担い手となる子供たちに知ることのおもしろさ、学ぶことの楽しさを知ってもらう一助になればという思いから企画されました。第13回となる今回は、喜田 宏会員が講演を行います。奮ってご参加ください。
事前申込制
会場:50名(抽選制・令和3年11月30日(火)締切)
※会場は中高生を優先いたします。
オンライン:250名(先着順)
※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催方法の変更、中止となる場合がございます。
※講演会後のアーカイブ配信は予定しておりません。
日時・場所
- 令和3年12月18日(土)午後2時30分~3時30分
- 日本学士院 会場地図
後援
台東区
台東区教育委員会
講演内容

喜田 宏会員
「人獣共通感染症とは? —次の世界流行(パンデミック)にどう備えるか—」
- 喜田 宏
- 日本学士院会員
- 北海道大学人獣共通感染症国際共同研究所 特別招へい教授 統括
世界は今、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに翻弄されています。SARSとMERSもコロナウイルス感染症です。また、エボラウイルスやジカウイルス感染症、パンデミックインフルエンザ、レプトスピラ病などが世界各地で発生し、人類を脅かしています。これらはすべて、自然界の野生生物または環境に静かに存続してきた微生物が、時に家畜、家禽そして人に伝播してひきおこす人獣共通感染症です。地球環境の激変によって、野生動物と人間社会の境界が消失した結果、微生物が家畜、家禽と人に伝播する機会が増え、人獣共通感染症が多発しているのです。次の人獣共通感染症パンデミックにどう備えるか、 考えましょう。
【講師について】
1943年生まれ。インフルエンザの疫学研究を地球規模で行い、ウイルスの遺伝子解析と感染実験の結果、夏にカモが営巣するシベリアの湖沼水中に存続しているウイルスが、渡りガモによって中国南部の池に持ち込まれ、そこでアヒル等を介してブタに伝播する経路を明らかにしました。さらに、ヒトと鳥のインフルエンザウイルスに同時感染したブタの呼吸器で新型ウイルスが出現する機構を実証しました。加えて、ウイルスの宿主域、病原性と抗原変異などの現象が、ウイルスと宿主細胞の遺伝子やタンパク質分子間の相互作用によって起こることを明らかにしました。これらの成果を基に、世界の高病原性鳥インフルエンザと新型ウイルス対策ならびに人獣共通感染症克服のため、広範な研究を展開し、国際協力研究にも多大な寄与をしています。
【日本学士院(にっぽんがくしいん)について】
日本学士院は、文部科学省に設置された、学術の発展に寄与するため必要な事業を行うことを目的とした機関です。本院は、明治12年に福沢諭吉を初代会長として創設された「東京学士会院」を前身とし140年以上の歴史を有しています。各分野で高い業績を挙げた研究者が会員として所属していますが、本院ではその研究成果を社会に還元することも学術研究者の一つの使命だと考えています。また、科学離れが叫ばれる昨今、その傾向に歯止めをかけ、将来の日本の担い手となる子どもたちに、今一度科学に対する興味を持ってもらう一助となればと思い本講演会を企画いたしました。一つの分野を究めた研究者の話を聞くことは必ず若い方たちの糧となることと思います。肩肘を張らずに聞ける内容となっておりますので、ご参加いただければ幸いです。
お申込み・お問合せ
<お申込み>
会場参加とオンライン参加でお申込み方法が異なります。
1. 会場 定員50名・抽選制・11月30日(火)申込締切
※会場は中高生を優先いたします。
e-mail、ファックスまたは往復はがきのいずれかの方法で、「会場希望」と明記のうえ、氏名(ふりがな)、 電話番号、メールアドレス等の連絡先を記載して、下記の連絡先にお送りください。抽選結果は12月上旬にお知らせします。
下記の申込みフォームからもお申込みできます。
会場参加申込みフォーム
2. オンライン 定員250名・先着順
下記URLよりお申込みください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LNuKmdB0RMC9SPEuaclk7A
<お問合せ>
日本学士院 事務室
- 〒110-0007 東京都台東区上野公園7-32
- TEL 03-3822-2101
- FAX 03-3822-2105
- 電子メール gkkouen2@mext.go.jp