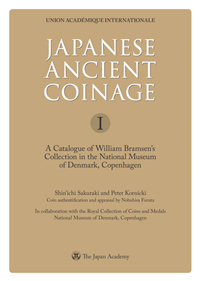ニュースレター No.33 会員寄稿
目次
会員寄稿
『古代ラテン語集成』とそのオープンアクセス化
松浦 純 会員
ドイツ文学専攻

昭和24年愛知県生まれ。東京大学教養学部教養学科卒業、東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。東京大学文学部助手、東京都立大学人文学部講師・助教授、東京大学文学部助教授・大学院人文社会系研究科教授等を歴任。フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞、恩賜賞・日本学士院賞等を受賞。
ラテン語は、もともとは、ローマを首都とするラティウム地域に居住していた人々つまり後のローマ人の言語でした。ローマが版図を広げ地中海世界を統一する大帝国へと発展するのにともなって、その世界の共通語となります。そしてローマ帝国の崩壊(西ローマ帝国滅亡476年)後も、イタリア語・フランス語・スペイン語などのロマンス系諸語の元となる一方、古典古代文化を直接伝える言語として、また西方キリスト教会の言語として、西ヨーロッパ世界の宗教、法、行政、学術などの共通語となり、「(西)ヨーロッパ世界」のまとまりを支える要となりました。その現代に続く直接の影響は、ロマンス系諸語はもちろんのこと英語にもラテン語起源の語彙が非常に多くある、といった点にまず見られます。しかしそれだけではありません。ドイツ語のような別の系統(ゲルマン系)に属するヨーロッパ言語の語彙や文法も、言語史の最初期に広範にラテン語に倣って形成された部分があって、「外来語」としての単語の流入などよりずっと深いレベルで、ラテン語が言語体系を規定しているのです。永らく学術言語として機能してきたことが、学名などにラテン語やラテン語式の造語が用いられることに現われているのは、言うまでもありません。ラテン語の語彙に少しでも触れることは、英語などだけでなく、さまざまな学名にも、また一味違った親しみを与えてくれるかもしれません。
『古代ラテン語集成』(Thesaurus Linguae Latinae 略称TLL)は、古風に直訳すれば『羅甸語之寳庫』あるいは『羅甸語寳物庫』といったところですが、西暦紀元600年頃までのラテン語語彙を網羅的に収録し用例とともに記述して語義の展開を詳しく示す、記念碑的大辞典です。紀元600年頃までということは、資料として、いわゆる古典期だけではなく、古代末期に至るまでのもの、したがってまたアウグスティヌスをはじめとするキリスト教古代教会の教父たちの著作も含まれる、ということです。それ以外にも、法律文書、医学文献、碑文、さらにはレシピなども含まれます。圧倒的な規模だけでなくこういったテクスト類型の包括性も、おもにキケロなど古典期の代表的文人のテクストを資料としていた19世紀までのラテン語辞典に対して画期的な点です。項目記述・編纂の基盤には、1000万枚に及ぶ用例・註釈カードの蓄積があり、各項目は執筆者・編集者・編纂主幹による何段階もの検討・確認を経てはじめて完成します。ブリタニカ百科事典が“dictionary”の項で次のように記していることも、国際的評価を端的に示すものと言えるでしょう。“Probably the most scholarly dictionary in the world is the Thesaurus Linguae Latinae.”
編纂は、1894年、前年のベルリン、ゲッティンゲン、ライプツィヒ、ミュンヘン、ウイーン五学士院の決定によって開始され、編纂所がミュンヘン(バイエルン学士院)に置かれました。第1分冊(a - abutor)の刊行は1900年でした。それを皮切りに刊行が続けられてゆきますが、2次にわたる世界大戦の破局を経て、1949年、編纂事業は国際事業として再出発し、バイエルン学士院に引き続き置かれつつ、ドイツ語圏諸学士院に加えて諸国の学士院・学術団体の国際協力を得て運営されることとなりました。参画機関はドイツの諸学士院(現在8院)を別にして原則的に各国一つとされており、現在は29か国38の学士院・学術団体(国際学術団体を含む)が加わっています。日本学士院は1987年に参加して現在に至りますが、欧米系諸国以外からはほぼ唯一の参加です。編纂作業には、現在20人余りの研究者があたっており、辞典項目執筆者の総計はこれまで390人近くに上っているということで、そのうち3人が日本の研究者です。
事業の歴史と概要、組織等について詳しくは、本院の『古代ラテン語集成案内』(1989 - https://www.japan-acad.go.jp/pdf/activities/TLL_brochure1989.pdf)をご覧ください。包括的な最新の紹介はバイエルン学士院ホームページにあります(https://thesaurus.badw.de/das-projekt.html〔ドイツ語〕、https://thesaurus.badw.de/en/project.html〔英語〕)。既刊の辞典項目は、A-M, n-netura, O-P, r-resurgo、および固有名詞篇(Onomasticon)C-D(こちらの続刊は予定されていない)です。このうち、刊行3年未満の部分以外は、pdfファイル形式(項目検索可能)で無料でオンライン利用できます(https://thesaurus.badw.de/tll-digital/tll-open-access.html)。
2019年に実現したこのオープンアクセスによって、古代ラテン語の最大・最良の辞典が自由に使えるようになったわけです。西洋古典学はもちろんのこと、西洋語学文学、西洋史学、西洋思想史・芸術史などの各分野にとって、またそれ以外でもラテン語語彙について調べたい場合に、たいへん大きな朗報です。日本学士院も協力しているこの辞典がわが国でも広く知られ、大いに活用されることを、国際協力委員会委員として期待しているところです。
会員寄稿
学士院紀要100巻記念によせて
柏原 正樹 会員
数学専攻

昭和22年茨城県生まれ。東京大学理学部数学科卒業。名古屋大学理学部助教授、京都大学数理解析研究所教授・所長、同大学高等研究院特定教授、国際数学連合副総裁等を歴任。平成19年より日本学士院会員。朝日賞、日本学士院賞、藤原賞、チャーン賞、京都賞、瑞宝重光章、京都府文化賞特別功労賞等を受賞・受章。現在Proceedings of the Japan Academy, Ser. AのExcecutive Editor。
日本学士院紀要出版100巻記念にあたり、学士院会員のなかで日本学士院紀要への投稿数がとりわけ多い(25編)とのことで、寄稿の依頼を受けましたので、書いています。ただ、誤解のないように申し添えますと、私の投稿したのはSeries Aで1編 6 頁以内と短いものです。
ご承知のように、学士院紀要はSeries AとSeries Bとに分かれており、その性格はこの二つでかなり異なっています。Series Aは数学の論文の出版に特化されており、さらに一論文の頁数も6頁が上限と制限されています。これは、Series Aが速報誌の性格を持っているからです。
フランス科学アカデミーの紀要Comptes rendus de l'Académie des sciences も同様に速報誌の性格を持っており、頁制限こそありませんが10頁以内が推奨されています。
一昔前までは、数学の分野においては、投稿してから出版されるまで数年かかることも珍しくありませんでした。そこで、速報誌に結果のみを投稿して、世界に情報発信することに大きな意義がありました。詳しい結果は、証明をつけて、別に原著論文で発表するという型式です。数学の論文では、証明が重要視されます。通常の学術誌に載る数学論文としては、結果だけを書いた論文、予想だけを書いた論文等々などは論外とされています。
このような意味で、学士院紀要のように結果だけを公表できる速報誌は、特に数学において大きな意義があります。しかし、世界的にみても速報誌の数は多くありません。
さて、私が学士院紀要に投稿するようになったのには、恩師佐藤幹夫先生(1926‐2023) の影響が大きかったと思います。佐藤先生、河合隆裕氏とともに、1970年代に超局所解析の共同研究に邁進していましたが、その成果を学士院紀要に速報の形で何度も発表しました。この頃は、3人の共同研究も急速に進展し、原著論文を書く暇も惜しいくらいの状態でしたので、学士院紀要の速報によって成果を公表するという恩恵に浴したことは非常に有難いことでした。
今からふりかえると、佐藤先生は、そのころ学士院会員であられた彌永昌吉先生(1906‐2006)から紀要への投稿を勧められていたという事情があったのではないかと推測しています。
その後も、折にふれ、紀要にしばしば投稿しています。そのほとんどは、速報の形での投稿で、結果のみを報告し、詳細は、別に出版するというものでした。なかでも、Pierre Schapira氏との共著で掲載した、層の超局所解析に関する論文2編は、これまでの解析学から幾何の性質を抜き出すことに成功した結果で、いまも表現論やシンプレクティック幾何学などに影響を与えています。その詳しい結果を書いた論文は、学術誌に掲載するには長すぎたので本の形にまとめて発表しました。
実は、学士院紀要に最初に関わったのは1968年に遡ります。その頃、小平邦彦先生(1915‐1997) が、米国から東大に帰られ、複素多様体の講義をされていたのを聴講していました。小平先生は、講義の中で時々問題を出されていました。学期の最後にレポートを提出しなければならなかったのですが、出題された問題の一つが解けたので、これをレポートにまとめて提出しました。すると小平先生に電話をするように事務から連絡があり、電話をすると、証明がおもしろいので、学士院紀要にレポートの結果を書かないかということでした。(小平先生も学士院会員でした。)その当時は、まだ学部学生でもあり、英語力もつたなく、論文の書き方もよく分からぬ若僧だったので、お断りしました。しかし今になって考えるとお引き受けした方がよかったかとも思います。
インターネットによって、学術誌の出版状況も大きく変わりつつあります。arXivのようなプレプリントサーバーもあらわれている現在、学士院紀要 Series Aも、変化を迫られています。しかし、査読を行う速報誌としての存在価値は失われていないと思います。これからは、それをさらに活用、発展していくことが求められると思っています。
会員寄稿
『日本古貨幣目録』をめぐって
佐藤 彰一 会員
西洋中世史専攻

昭和20年山形県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業、早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。愛知大学法経学部助教授、名古屋大学文学部・大学院文学研究科教授等を経て、平成21年より日本学士院会員、平成31年よりフランス美文・碑文アカデミー外国人会員。令和元年より国際学士院連合副会長を務める。
2019年11月25日から29日にかけて、パリのフランス学士院を会場にして、国際学士院連合(UAI)第90回総会が開催された。この会は同時にUAI創立100周年を祝賀する会でもあった。この記念すべき総会で、日本学士院が提出していた新しい学術プロジェクト「日本古貨幣目録」が、94番目のプロジェクトとして採択された。この新プロジェクトの構想は、それを遡ること数年、学術先進国である日本の学術プロジェクトが、第7プロジェクトの「在外日本関係史料翻刻と翻訳Unpublished historical documents relating to Japan in foreign countries 」だけというのはいかにも淋しい、ついては何か新しいプロジェクトを立ち上げて欲しいというUAI事務局の意向を受けて、いろいろ模索した結果、今の日本の人文科学分野で他国(主に欧米)の斯界での学術動向に鑑みて、我が国において一段の推進を必要とする分野が何かを考えたとき、浮上してきたのが「貨幣学(古銭学)numismatics」の分野であった。
筆者が専門としている歴史学(西洋中世史)は、この学問を遂行する上での知識と専門技術を教授する個別の分野として、特に古い時代に関しては考古学、碑文(金石文)学、中世や近世に関しては史料学(これは更に古書体学、文書形式学等々の細目分野に分かれている)など古記録を正確に解読するのに必要な、かつては「補助科学」と称された個別の研究領域が存在するが、このなかで欧米の先進国で盛んでありながら、日本では近年にいたるまで比較的等閑に付されている分野がある。それが「貨幣学」である。
日本における貨幣の歴史については、第一分科の同僚である東野治之氏が著した『貨幣の日本史』(朝日選書1997年)と題する、タイトルが示すような日本貨幣の歴史についての優れた概説があるものの、モノとしての貨幣それ自体の探究、すなわち「貨幣学(ニュミズマティクス)」の体系を論じた著作ではない。著者もそのような著作として執筆する意図はなかったであろうと推察する。この書物のなかで縷々説かれているように、古銭に対する人々の関心は高く、とりわけ江戸時代には古銭の蒐集家の交流が盛んで希少な銭貨の売買や交換、古銭についての情報交換が盛んで、そうしたなかで蒐集家大名として名を馳せたのが福知山藩主朽木昌綱であった。彼のコレクションは、現在大英博物館とオクスフォード大学のアシュモリアン博物館に収蔵されていると承知しているが、朽木昌綱に代表される江戸期の古銭蒐集家の執筆活動も旺盛であった。しかしながら、明治期に入り東京帝国大学の史学科の創設と、そこでの教育において、先ほど申した歴史学の「補助科学」すなわち古書体学(我が国では古筆学とも称される)や文書学の教育はカリキュラムの一環として整備されたものの、古銭の学問「貨幣学」はついぞ正式の「補助科学」として採用されることはなかった。その理由は幾つか考えられるが、そのひとつに古貨幣が趣味と実益に関わっていて、明治の研究・教育者たちは、そうした分野と学術研究が接点をもつことへの忌避感があったのではないかと思われる。
翻って欧米の歴史研究の分野では、歴史史料としての古貨幣は非破壊検査技術の発達のおかげもあって、貴金属の含有量の変動などの調査などを通じて、経済史研究の重要な素材となっており、また貴金属の地理的由来を通じて、グローバルな経済活動を解き明かすためになくてはならない情報を提供してくれる。また金か銀か素材の異なる貨幣の交換比率の確定によって、所与の時代の異なる経済圏どうしのリンキングの様相も知ることができる。このようにモノを基盤とする歴史研究にとって、「貨幣学」的アプローチは今やなくてはならない分野になっているのである。我が国の大学で「ニュミズマティクス」が正式な授業科目になっている例を、私は寡聞にして知らない。経済史の授業のなかで、「貨幣」現象に触れられることはあっても、体系的な知識の教授が行われている例はないのではないかと推測している。
だが、近年になって少しずつ「貨幣学」分野への関心を強め、これに取り組んでいる研究者の姿が日本史、東洋史、西洋史いずれの分野でも見られるようになった。そうした機運をさらに盛り上げるために、日本古貨幣の目録を作る作業は、この学問の足場を固める上で重要であるという認識に立って、UAI事務局の要請もあり、正式の新学術プロジェクトとして申請し、先に述べたように2019年11月の総会で第94プロジェクトとして採択された次第である。
*
新プロジェクト申請にあたっては、これに先立つ数年間を予備調査に当てた。日本貨幣のコレクションを持つ西宮市にある「黒川古文化研究所」、佐倉市にある「国立歴史民俗博物館」、名古屋市にある三菱UFJ銀行(旧東海銀行貨幣コレクション)、東京大学経済学部所蔵日本貨幣コレクションなどを、事務室の竹内基樹さんと共に視察し、当該機関の専門家と意見交換し、その多くの方々に「日本古貨幣目録諮問委員会」のメンバーになって頂いた。プロジェクトの展開戦略として、最初からあまりに大規模なコレクションと取り組むよりは、具体的な成果を比較的挙げやすい、海外の日本古貨幣の目録を対象にするのが妥当であると考え、大英博物館所蔵日本貨幣目録の作成に参加した実績があり、ケンブリッジ大学に留学し彼の地の古銭学者に知己が多い櫻木晋一氏(現在、朝日大学教授)に実務の責任者をお願いした。
櫻木教授は早い段階で最初の目録作成の対象として、明治期に「お雇い外国人」として来日して、日本の古代史研究に画期的な功績を残し、かつ優れた日本古貨幣蒐集家でもあったウィリアム・ブラムセンが残し、現在コペンハーゲンにあるデンマーク国立博物館に収蔵されているコレクションの目録作成を考えていたようである。デンマーク側および共同執筆者のピーター・コーニッキー、ケンブリッジ大学名誉教授の熱意ある協力のおかげもあって、作業は順調に進み、全編英文による『Japanese Ancient Coinage vol. 1, A Catalogue of William Bramsen’s Collection in the National Museum of Denmark, Copenhagen』が2023年6月に刊行された。
出版元をどこにするかで思い悩んだ末に、筆者が現役時代に2期にわたりCOEプロジェクトの責任者を務めた折に、国際研究集会のプロシーディングをはじめとする種々の印刷物の作成を通じて、その優れた造本センスとサンスクリット語やチベット語を含め多言語印刷に秀でた能力を持つ名古屋の出版社「あるむ」にお願いすることにした。こうして完成したカタログの出来栄えは、自画自賛とのお叱りの言葉を受けるのを承知のうえであえて言うならば、見事な完成度を示していた。表紙の基調になっている金色は、黒を含めた四色分解で行うカラー印刷の色彩調整のなかでも最も難しい作業とされているが、金色の色感を絶妙に実現し、大文字のみのフォントであるトロイ書体の採用と相まって重厚ななかにも、「黄金の国ジパング」の貨幣コレクションであることを的確に伝え、角型背表紙の採用もあって、瀟洒な風格を具えている。無論、櫻木晋一、ピーター・コーニッキー両氏の手になるカタログ本文、解説も非常に充実した内容であり、献呈した海外の識者や専門家から過分な賞賛の言葉を忝くした。
本カタログへの評価の高さは、これによって両著者がデンマーク国立博物館賞を受賞したことにも表れている。このカタログ出版によって、我が国の古貨幣研究者、好事家の皆さんに、ブラムセン・コレクションの内実が初めて明らかにされ、ブラムセンの蒐集家としての眼力の確かさと、コレクションの質の高さに驚嘆した専門家もおられるということである。加えて著者のひとり櫻木教授は、ロンドンの由緒ある王立古貨幣協会(The Royal Numismatic Society)の2023年の同協会メダルの受賞者となった。このメダルは世界で古貨幣研究に顕著な功績があった人物ひとりに与えられるもので、日本人で初めての受賞であった。評価された功績のなかには数年前に同教授が参加した『大英博物館所蔵日本貨幣カタログ』編集への貢献もあったであろうが、決定的であったのはブラムセン・コレクションのカタログ編集であったことは、時期的な符合から容易に推測できることである。
*
私どもの次の作業は「日本古貨幣カタログ」第2巻の作成であるが、これについては対象がほぼ確定している。フランス国立図書館貨幣・賞牌部門が所蔵している日本古貨幣のカタログ作成である。これを実現するための最大の懸案は、カタログ作成の費用をどう捻出するかである。
ブラムセン・カタログの場合もそうであったが、調査のための研究・旅行費用は、日本学術振興会との共同事業による委託費と、櫻木教授個人が獲得している各種の研究費で賄われた。カタログ作成は上記日本学術振興会の委託費が充てられた。しかし、日本学術振興会からの委託費はブラムセン・カタログの出版費用で終わり、第2巻の出版費用については、当面目処は立っていない。櫻木教授の話では、フランス国立図書館所蔵の日本古貨幣に関しては、以前から調査を行なっており、かなりの段階までデータ整理を済ませており、出版の道筋が見えているとのことである。残るはフランス側が高水準で古貨幣の写真撮影をしてくれることと、カタログの出版の費用問題である。
諸方に費用獲得のための努力をする所存ではありますが、「日本古貨幣カタログ」プロジェクトの推進と、我が国におけるこの分野の発展にご賛同いただける皆様に、ご協力頂ければ洵に有難く存じます。