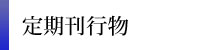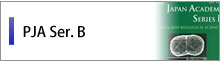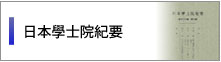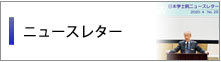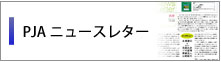日本学士院第15回学びのススメシリーズ講演会のお知らせ

パンフレットダウンロード
日本学士院学びのススメシリーズ講演会は、様々な分野で素晴らしい研究を重ねてきた日本学士院会員が、日本の将来の担い手となる子供たちに知ることのおもしろさ、学ぶことの楽しさを知ってもらう一助になればという思いから企画されました。第15回となる今回は、金水 敏会員が講演を行います。奮ってご参加ください。
事前申込制
会場:100名(先着順)
会場参加申込みフォーム
オンライン:500名(先着順)
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_85tI0T19SGelimZUFIAOvg
※講演会後のアーカイブ配信は予定しておりません。
日時・場所
- 令和5年12月16日(土)午後2時30分~3時30分
- 日本学士院 会場地図
後援・協力
後援:台東区、台東区教育委員会
協力:上野の山文化ゾーン連絡協議会
講演内容

金水 敏会員
「物語を彩る「キャラクター」と「役割語」」
-
金水 敏
- 日本学士院会員
- 放送大学大阪学習センター所長
- 大阪大学名誉教授
「そうじゃ、ワシが知っておるんじゃ」というセリフを聞けば老博士、「そうですわ、わたくしが存じておりますわ」というセリフを聞けばお嬢様、というように、人物像から連想される話し方を「役割語」と呼びます。日本語には多くの種類の役割語が存在し、マンガ、アニメ、絵本、ドラマ等で活用され、物語の理解を助ける働きをしています。役割語はどのようにして生まれ、発達してきたのでしょうか。また、日本語以外の言語には役割語は存在するのでしょうか。本講演では、このような問題について、夏目漱石、芥川龍之介の小説や名探偵コナン、ジブリアニメなど、身近で親しみやすい作品の例を用いながら、役割語の謎について探っていきます。
【講師について】
1956年生まれ。「ある」、「いる」、「おる」といった日本語の存在動詞の意味や用法がどのように変化してきたのかを明解に示すとともに、その研究の中から新たに役割語という概念を導き出し、役割語がどのように成立し、また、小説やマンガやアニメなどのメディアの発達と深い関係を有しているかを明らかにしました。
著書に『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』(2003年、岩波書店)や『コレモ日本語アルカ?—異人のことばが生まれるとき』(2014年、岩波書店)などがあります。
【日本学士院(にっぽんがくしいん)について】
日本学士院は、文部科学省に設置された、学術の発展に寄与するため必要な事業を行うことを目的とした機関です。本院は、明治12年に福沢諭吉を初代会長として創設された「東京学士会院」を前身とし140年以上の歴史を有しており、各分野で高い業績を挙げた研究者が会員として所属しています。
お申込み・お問合せ
<お申込み>
会場参加とオンライン参加でお申込み方法が異なります。
1. 会場 定員100名・先着順
会場参加申込みフォーム
※お申し込みフォームをご利用になられない方は、e-mail、ファックスまたは往復はがきのいずれかの⽅法で、「会場希望」と明記のうえ、⽒名(ふりがな)、 電話番号、メールアドレス等の連絡先及び中学生/高校生/一般の別を記載して、下記の連絡先にお送りください。
2. オンライン 定員500名・先着順
下記URLよりお申込みください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_85tI0T19SGelimZUFIAOvg
<お問合せ>
日本学士院 事務室
- 〒110-0007 東京都台東区上野公園7-32
- TEL 03-3822-2101
- FAX 03-3822-2105
- 電子メール gkkouen2@mext.go.jp