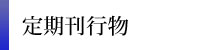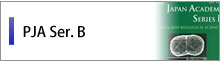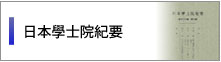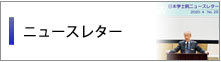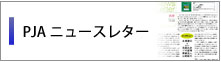日本学士院客員の選定について
日本学士院は、平成22年9月13日開催の第1041回総会において、ウィリアム・セオドア・ドゥ・バリ氏を日本学士院客員に選定しましたので、お知らせいたします。
| 氏名 |
ウィリアム・セオドア・ドゥ・バリ教授
Prof. William Theodore de Bary |
 |
| 現職 |
コロンビア大学John Mitchell Mason Professor |
| 居住地 |
米国 ニューヨーク市在住 |
| 専攻学科目 |
儒教哲学、日本思想史 |
| 生年 |
1919年(91歳) |
| 略歴 |
1941年 コロンビア大学BA取得
1948年 コロンビア大学大学院入学
1953年 Ph.D.
1953年 コロンビア大学教授
1969-1970年 米国アジア学会会長
1971-1978年 コロンビア大学副学長
1979年- コロンビア大学John Mitchell Mason Professor 1999年 米国哲学会名誉会員 |
| 主要な学術上の業績 |
ウィリアム・セオドア・ドゥ・バリ教授の研究は、二つの側面を持っている。一つはNeo-Confucianismと呼ばれる儒教哲学の研究である。この考えは「為己の学」(自己の内面の声に耳を傾けるという学問)という意であって、この考えは『為己の学』“Learning for One’s Self ” 1991という著作に凝縮されている。
もう一つは黄宗羲の『明夷待訪録』と本についての研究であって、この本はde Bary教授の若い時の博士論文である。教授はこの論文をすぐ出版することなく、一方では“Waiting for the Dawn - A Plan for the Prince”というタイトルの格調高い本に翻訳し、何十年とその推敲に努めながら、他方では日本、中国、米国(多くの中国の人が米国の大学に勤めている)の黄宗羲研究を調べていった。その中で最もde Bary教授の研究に役立ったのは、島田虔次教授の愛弟子小野和子教授の研究であった。de Bary教授の緻密さと研究の徹底ぶりには驚くべきものがある。
前者は島田虔次教授の『中国における近代的思惟の挫折』(筑摩書房、最近平凡社の東洋文庫に収められている)という本であって、これは多くの後進に影響を与えた名著である。島田虔次教授は自分の仕事を体系化することはなかったが、de Bary教授は明の思想に存在する自己の捉え方が、人類に寄与することに気がついた。その後、島田教授を知り、かつその著作を読んで、自分の直感が正しかったことを知り、これを体系化して「為己の学」という学問を形成した。これは人類の自己の捉え方の歴史の上で、大きな功績と言わねばならない。
ここに見られるように、de Bary教授は自身のこの主著を、島田虔次教授とその弟子小野和子教授の研究に多くを負っている。ここに見られるように日米間の学問的な交流は予想以上に深いのである。 |